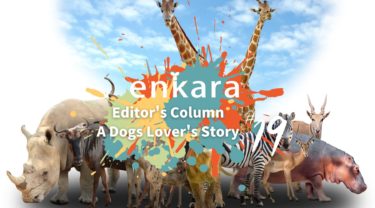2019年に改正された「動物愛護管理法」によって、今年6月から”マイクロチップの装着”が義務化されます。しかしこれは、日本国内に暮らす全ての犬が対象ではありません。誰を対象としていて、私たち飼い主は何を行う必要があるのか__ マイクロチップの装着については、飼い主それぞれに様々な考えがあって然るべきだと思います。しかし現在、愛犬と共に日本に暮らす以上「動物愛護管理法」という法律で決まっていることは誠実に守らなければなりません。今回は、新たに決まったマイクロチップ装着・登録のルールについて、私たち飼い主にとって必要なポイントをまとめてみました。